-
「身体の中で曲がるところを関節と言います。そこを上手に動かすようにするにはどうしたらいいでしょうか?」「その近くにあるものを使います。そうです。肉を使うのです。筋肉と言います。筋肉を上手に使って身体を動かします。」「今日はラジオ体操の練習をしますが、上に真っ直ぐに腕を伸ばすときは、この力こぶが耳につくようにしましょう。そうすると姿勢良くピンと身体全体が伸びます。手を横に広げる運動もありますね。その時は手のひらを上にしましょう。そして、身体よりも少し後ろに腕がいくように意識してひろげましょう。今日はこの二つだけ気をつけてやってみます。」気をつけるポイントが絞られたので、子どもたちはそこだけは意識して身体を動かすことができているようでした。ラジオ体操の動きにもたくさん教えたいポイントがありますが、たった二つだけ意識するだけで全体的に正しい運動できれいな体操になっていました。

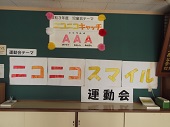
左:ラジオ体操の様子 右:運動会スローガン
-
運動会の特別時間割が始まりました。今年の運動会も考えられる限りの感染予防対策をした上で、種目数を絞って実施します。子どもたちは、学校行事でも様々なことを学び成長します。友だちと同じ目標に向かって練習することで、一人では出来ない事も初めてできるようになることもあります。地域の方や多くの保護者の皆様に観ていただくことはできませんが、制約のある中、自分で考えて動くことで子どもたちにもたくさん成長する姿が見られると考えています。今朝は全校集会で感染予防について話しました。ずっとマスクの生活を続けてきて「これくらい大丈夫なんじゃない」と油断してしまわないように、換気、手洗い、うがい、最低1m以上の間隔、遊び方、登下校の仕方等について再確認しました。また、マスクも不織布のような感染リスクがより低いものを使っていくように話しました。子どもも職員もみんなで気をつけて児童会目標「ニコニコキャッチ トリプルA(あいさつ 安心 安全)」の学校生活を創っていきたいです。


左:強風等で落下の危険がある校庭の桜の枯れ枝を伐採していただきました。幹にうろがあるような桜ですが、下の幹はまだ勢いがあるので、根元から切り倒すことはしませんでした 右:3年生「夏の絵」模造紙3枚分の共同作品です
-
いつも朝からサッカーをしている子どもたちがいます。2学期になってから、参加する子どもの人数も段々増えてきて試合形式で遊べるようになってきました。上手にボールを扱える子もいれば、ボールに触れることができない子もいます。ですが、みんな一つのボールを追いかけて楽しんでいます。今朝の試合でボールを相手に取られ、ゴール直前まで迫られた時のことです。「最後まであきらめるな!!」と大きな声を出して同じチームの子に呼びかけている子がいました。今までだと、ボールを奪われたらそのまま相手がゴールするというのが、お決まりのパターンでしたが、取られても奪い取りにいく姿が見られるようになったのです。おそらく社会スポーツでサッカーを習っている子が、普段監督に言われていることを友だちにも言うようになったのだと思います。この子の一言が遊びでやっていたサッカーの質を変えました。子どもは学校の中だけではなく、いろいろなところで学んできます。お互いの学びを出し合い、学び合うのも学校の大切な役割です。



ひまわり学級でカレー作りをしました。自分たちの育てた野菜を使ってカレーを作ると春から計画してしていたのです。一人ずつ自分専用の調理机とコンロを使い、自分だけが食べるカレーを作ります。お友だちのカレーを食べられないのは残念ですが、丁度収穫できたスイカもデザートに食べることができました
-
2学期が始まって1週間が過ぎました。学校のペースを取り戻し、朝からグランドで遊ぶ子も増えてきました。「ひとーりだしはおにだぞよい」のかけ声とともに始まった鬼ごっこ。ちょっとしたことで、言い合いになり雰囲気が悪くなりました。どうするのかなと思っていたら「じゃあさ、次はぼくがやるからそれでいい?」とちゃんと仲裁に入る子がいました。再スタートすると、さっきの言い合いのことはすっかり忘れて遊んでいます。子どもの世界で解決することもたくさんあり、子どもだけで上手にやり取りが進むこともあります。遊びながら大切なことを自然に身につけています。帰りに「じゃあ、7時30分にね」と遊ぶ約束をして帰った子どもたちがいました。こちらは、ネットを使った遊びの約束のようでした。平日の夜7時30分から友だちと遊ぶことができるような時代に変わってきていますが、きっとその遊びの中にも自然に身につくことがあるのだろうと思っています。 写真:低学年の運動会表現の練習風景

体育館の全てのドア、窓を開け、大型扇風機3台を使用して換気し、お互いの距離を確保して練習しています
-
全校音楽で「リズム打ち」をしました。1・6年、2・4年、3・5年の3つのパートに分かれて、それぞれ違うリズムを手拍子します。休符のところは叩かないので、「ウン」と心の中でカウントして手を大きく広げて休みます。4分音符は「タン」、8分音符は「タカ」の言葉に合わせて手拍子するとやりやすかったです。それぞれのパートを聴いた後、全校で合わせます。主旋律のメロディーは「パプリカ」でした。キーボードの音を聴いてしまうと、テンポが合わなくなったり、休符でうまく休めなかったりしそうでしたが、子どもたちは余り難しく思わなかったようです。リズムに言葉をのせる「ラップ」のような音楽を普段から耳にしているせいかもしれないと思いました。


左:全校音楽の様子 右:夏休み中にたくさん増えて困っている雑草の観察スケッチをしていました。最近は、iPadで記録することもありますが、自分の目で細かいところまでよく見て、描いて、色づけをしていく方法は、頭の中に記憶させていく意味からもとても大切です