-
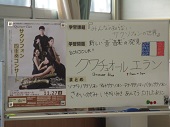


個別懇談会が始まっています。子どもたちの頑張っている姿を担任がお伝えし、保護者の皆様と一緒に成長を共有したいという願いもあります。それと同時に相談事も一緒に考え合っていくきっかけにもしたいと思っています。児童心理学の講演会で「脳は一生成長していく。そのためには、いいこともわるいことも交互にバランス良く体験していく必要がある」と学びました。成功体験だけでは、失敗したときにそれを乗り越えることができなくなってしまう可能性があるというのです。失敗することを恐れて何もやらないよりも、失敗を重ねながら成功していくことが大切なのだと思いました。子どもたちは、日々何かの困難にぶつかりながら生活しています。大抵は、今までの経験から乗り越えられますが、本当に困ってSOSを出したときは周りの大人の出番です。支えてあげて乗り越えることで成功体験になります。上手に見守り、子どもたちの声を聞き取れるようにしたいです。 写真:11/26 アウトリーチコンサート サキソフォン4重奏グループの演奏を聴きました
-

今日の4時間目は1年、3年、4年が「国語」の勉強をしていました。1年と3年は「新出漢字」を学んでいました。1年は「名」です。乱暴な言い方をすれば、カタカナの「タ」と漢字の「口」を組み合わせた字です(実際にそうやって学習する方法もあります)。1マスを4分割したシート(マス)にバランスよく書くことに気をつけていました。3年は「炭」「庫」「羊」「勝」を学んでいました。辞書を手元に置き、新出漢字を使った熟語をどんどん出し合っていきます。黒板は出来た熟語で一杯になりました。どうやって使われるのかや今まで知っていたことと結びつけて漢字を覚えていました。4年は、授業の始めに漢字の小テストをしていました。覚えた漢字を確実に自分のものにしていく一つのやり方です。漢字ドリルはタブレットでも学習できるようになっているようですが、見て、読んで、書くことをどのクラスも大切にしています。 写真:6年生が大縄跳びの練習をしていました。自分たちで縄も回しています。昨年は、連続2000回以上跳んでいます。最後の年、どこまで記録が伸びるか楽しみです
-



朝の時間に全校体育で「大縄跳び」を行いました。学年ごと1本の大縄を跳びます。1年生は、練習している内に跳ぶタイミングがだんだん分かってきたようです。連続で32回跳べた時がありました。2年生は8の字で跳んでいました。全員が跳べるのですが、他の学年の様子を気にしてよそ見をしている子はタイミングが合わなくなります。集中力を高めるとさらに回数が伸びると思いました。連続で134回、5分間で226回跳ぶことができました。短縄も大縄も子どもの時に経験しておくことが大切です。いろいろな跳び方にチャレンジしてほしいです。 写真左:1年生の様子 縄を回すタイミングも大事です 中:3・4年生は合同で行っていました。かけ声をかけて楽しそうです 右:さすが5年生。回す速さが違います。県のチャレンジにも応募できるかも
-



名前を知らない四年生のお兄さん、お姉さんといっしょにアルミホイルをまくときにむねがドキドキしました・・・」4年生との焼きいも交流会をした後の2年生の感想文です。今の2年生は入学した時から、校内の交流会や縦割り班活動、全校集会での関わり等が出来ていない学年です。だから、本校のように小規模の学校であっても1、2年生が高学年のお兄さん、お姉さん達の「名前を知らない」ことはあるのだということがわかりました。今は、感染予防対策をして集会等も行うようにしてきていますが、まだ本来の形に戻すところまではいきません。子どもたちへの影響の大きさをあらためて感じました。12月は「児童会まつり」も実施します。全校での交流をすすめていきます。 写真左:6年生修学旅行 カモメに餌をあげています 中:富士山もきれいに見えました 右:5年生が収穫祭を行いました。全員餅つきを体験しました
-

1年生が繰り下がりのある引き算の学習をはじめました。例えば「15-8」のような計算です。「「5-8」は引けないから、15を10と5にわける」ところから始めます。数字だけで説明しようと思えば出来てしまうし、わかった気にもなってしまうのですが、大事なのは具体的にイメージできるかどうか、日常生活と結びつけて考えられるかどうかだと思います。頭だけの理解は忘れやすいので、最初はおはじきや数え棒やブロックを使って学習していきます。今までの10の合成と分解もわかっていないとできません。算数は今までの学びの積み上げが大事な分野もある勉強です。 写真:竹馬で遊ぶ児童 自分の肩の高さ位ある竹馬を6年生が乗っています。人が出来ると自分もと練習していました