-
3年生図工の公開授業研究会がありました。前回は共同製作でしたが、今回は個人製作の授業です。子どもたち一人ひとりが「これぞ夏!!」と感じるものを絵にします。紙の種類、紙の色、画材、使う用具も多数用意して、自分のイメージに一番合っているものを自分で考えて選びます。おいしそうな「かき氷」を描こうとした子どもは、シロップのブルーハワイの青色の表現にこだわりました。色をつけるために、筆やスポンジを描く場所によって使い分けます。色の濃さは水の量で調節していました。氷のつぶつぶは点で描きその上からベタで着色する等、今までの経験も総動員して自分のイメージ合う「かき氷」に仕上げることができました。夏休み明けに一つの大きな共同作品にする予定です。完成が楽しみです。



左から:「ブルーハワイのかき氷」、「大きくて強いカブトムシ」、ヒマワリは、とろとろ粘土に絵の具を混ぜて作った色を指で直接描いていました。少し盛り上がって着色されるので、花びらの様子を上手に表現することができていました
-
「あっ、蝉だ。蝉がいる」「ホントだ。でかい」「あっ、飛んだ、飛んだ」朝から、クラス内に忍び込んだ蝉を見つけて喜んでいる声が2階から聞こえてきました。週明けは、朝から畑に行って自分たちが育てている作物の世話から始まる学年が多いです。この間は、「どうも畑に猿が出るらしい。ミニトマトが散らかっていた」という話もあり、害獣をどう防ぐかも考えなくてはなりません。効果があるかどうかわからないけれど、ネットを張り巡らせた学年もあります。豊かな自然の中で生活するということは、いろいろな生き物たちとともに暮らすということです。悩みや心配事があったとしても、都会では味わうことができない生活です。身体も心も大きく豊かに育ってほしいと思っています。


水泳参観日でした。1・2年生もビート板を使って、上手にけのびをしていました。今は、ゴーグルを使うことが当たり前になっているので、「水の中で目を開ける」ということも抵抗なくできています
-
7月のお誕生日インタビューの中で「一学期に楽しかったことは何ですか?」がありました。放送を聴いていると半分の子が「プールです」「水泳です」と答えていました。水の中は非日常の世界なので、楽しいと思う子どもが多いです。水が苦手な子も、自分のできそうなことからスタートして、遊びながら慣れていくと楽しくなってきます。学年が進むにつれて、自分のめあてもハッキリしてきます。学校のプールで25mを泳ぎ切る力がつくことは、子どもたちにとって一つの目標です。水泳参観日に子どもたちの頑張っている姿を観ていただきたいと思います。



左から:チャレンジコーナーで作られていた形です。休み時間に遊んでいます 右:「ヒマワリ」を飾っていただきました。花壇にある3年生のヒマワリもグングン伸びています
-
全校運動で大縄跳びをしました。「8の字大縄跳び」で5分間に何回跳べるか、クラス毎に挑戦です。1・2年生は合同でおこなっていました。5、6年生は大縄も自分たちで回します。2回チャレンジしましたが、どの学年も2回目に1回目の記録を更新していました。自分たちで声を出して数を数え、1本の大縄に集中して、みんなでやり遂げることは、子どもたちにも手応えと満足感のあることでした。3年生は「100回」を越えるととても喜んでいました。Web上では、全県の記録会も開催されています。挑戦するクラスが出てくるといいなと思いました。



左から:6年生、4年生、1・2年生の様子。昨年度、6年生は連続跳びで2000回を越える校内記録を持っています。回し方も上手で、跳ぶ速さもダントツでした
-
7月に入ってから朝の時間や休み時間に楽器を演奏する音が聞こえてくるようになりました。11月に行われる音楽会の曲がそれぞれの学年で決まってきたからです。そして、合奏でも自分の演奏する楽器の担当が決まったので、子どもたちは自主練を始めているのです。登校途中にも「ぼく、今年はドラムなんだよね」と自分が担当する楽器について話題にしている子がいました。昨年はソロ演奏のパフォーマンスをする学年もあり、少ない人数なので一つ一つの楽器の音は大きな役割を果たします。子どもたちが張り切っていて、今から本番がとても楽しみです。

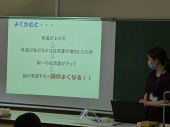
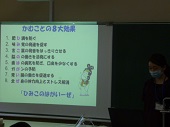
今日は2学年ずつに分かれて歯科指導をしていただきました。高学年の様子です。「よくかむと・・・頭がよくなる」「かむことの8大要素 ひみこのはがいーぜ」