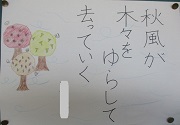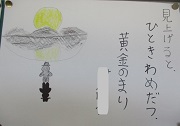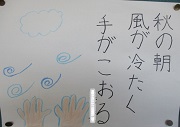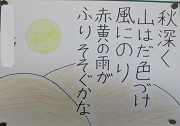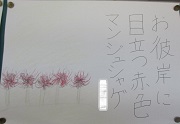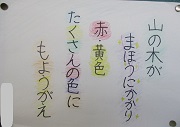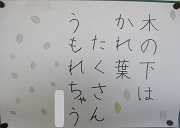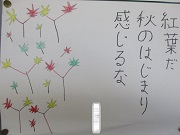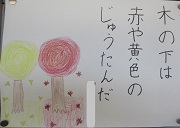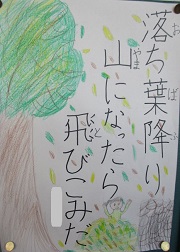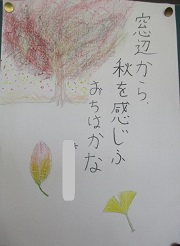-
昨日、2年生は手話のことを学びました。教えてくれたのは、上伊那聴覚障害協会の会長さんと手話サークルの方、そして社協の職員さんです。2年生は事前に「手話ができたらこんなことができるかも」と考えいたそうです。・「ママにないしょでパパに・・・」・「授業中におしゃべり・・・」・「友だちに答えを教えてもらえる・・・」のように、話さなくても内緒でいろいろなことができることを楽しみにしていたようです。ところが、会長さんから普段の生活で不自由なことや困ることについてのお話をお聞きしたり、自分の名字を手話で教えていただいたりしてできるようになった子どもたちは、次のようなことを考えたそうです。手話ができたら、・耳が聞こえない人とお話しができる・誰でも手話ができれば、長谷小に来られる(聾学校へ行かなくても、長谷小に通学できる)・耳が聞こえなくてもお友だちになれる・ろうがっこうの人とお友だちになれる・・・等。聴覚障害者の方に出会い知り合うことで、人とのつながりを拡げようと考えることができた子どもたち。素敵です。



クリアシールドを持参していただき、口元が見えるようにお話ししていただきました。誰もが不自由なく生活ができるように、私たちはもっともっと知る必要があることを感じました。
-
マラソン記録会まであと8日。今年は、記録会までに全校で3000周することを目指して練習しています。大きなカードには、グランドを10周すると1マス分好きな色を塗ることができます。朝のマラソンタイムが終わると、大きなカードに子どもたちがどんどん色を塗っています。全校で頑張っていることが目に見えてわかります。11月6日に1400周までいきました。どこまで進むことができるのか楽しみです。



よーい、スタートで10分間。自分のペースで走ります。 中:1年生は、1周目からかけっこのように全速力で走ります。まだ、「長く走る」ペースがわからないので、いつも全力です。かわいいです。右:3年生が「光」の学習をしていました。鏡を使って、日光を反射させていきます。地面に光の道ができていました。
-
4年生になると、学校で使っている自分の机の天板を張り替えます。「木育」として市が行っている授業です。今日は4名の講師の方に来ていただきました。最初に山の大切さについて学習しました。木の種類は大きく分けて2つあることや「水」に関する大切な役割を果たしていること等を教えていただきました。その後、電動ドライバーを使って自分の机の天板を張り替えます。真新しい机の天板になった自分の机で明日からたくさんのことを学んでほしいです。






上段から:4年生「木育」の様子 下段中:3年生が絵画回覧作品を鑑賞していました。気に入った作品について、感想を伝え合っています 下段右:今朝は冷え込みました。学校の畑には大きな霜柱がありました
-
今日からマラソン記録会に向けて全校で走ります。マラソンカードに校庭を何周したか記録して、自分の頑張りを後で振り返ることができるようにします。勝負するのは自分自身とです。昨年の記録よりも何秒縮めることができるのか、そして何よりも走ることを楽しむことができるかどうかが大切です。楽しむためには、ちょっぴり頑張ることも必要です。子どもと一緒にしばらくの間は、みんなで走ることを楽しみましょう。



一緒に走りながら、振り向いて6年生にカメラを向けたら、余裕で「イェーイ!」と言って走り去っていきました。昨日の音楽会が大成功に終わり、充実感一杯の様子です
-
いよいよ明日は音楽会。会場の準備も、子どもたちの準備も整いました。明日は、全校で音楽を楽しみます。



左:昇降口前に飾られた「音楽会でがんばりたいこと」 中:ステージ装飾は、長谷の山と美和湖と秋の紅葉をイメージしています 右:5年生「いぶき組」が音楽会後に販売する「いぶき米」の準備をしていました
-
いよいよ音楽会の週になりました。子どもたちは、発表に向けて既に1ヶ月以上練習を積み重ねてきています。今日は、外部講師として宮尾先生に全学年ご指導していただきました。演奏や歌声はもちろんですが、その前に「長谷小の子どもたちの返事や挨拶が素晴らしい」とほめていただきました。日頃から子どもたちが意識して生活していることを認めていただいて嬉しく思いました。演奏や歌声については、大事なポイントを重点的に指導していただけたので、レベルアップできたようです。当日は、どの子も精一杯の姿を見せてくれると思います。



低学年も高学年も先生のアドバイスをよく聴き、自分たちの歌声や演奏がもっと良くなるように学んでいました。当日も、今日のような秋晴れであることを願っています
-
以前にもお知らせしましたが、長谷の子どもたちもようやく外遊びが多くなってきました。サッカー、滑り台、ブランコはもちろんですが、タイヤ跳びやタイヤの上でジャンケンをするゲーム、ジャングルジム、鉄棒、雲梯等、休み時間、朝の時間、放課後の時間に遊んでいます。コロナ禍の影響もあると思いますが、今まで遊ぶことが少なかった分、遊んでいてケガをする子どももいます。楽しいことは、ちょっぴり危なさがあるから楽しいのです。たくさん遊んで、自分にとっての危険回避の方法も身につけてほしいと願っています。




上段左:大賑わいのジャングルジム 中:鉄棒でみんなコウモリに 右:タイヤ跳びの両端からやってきて出会った場所でジャンケンをします この3枚は教頭先生のスナップ写真です。ナイスショット! 下:放課後の時間に「今度はだるまさんが転んだをやろうぜ」と5年生の男の子が声をかけて始まった「だるまさんが転んだ」の様子です。グランドの端まで聞こえる大きな声で「だるまさんがこ・ろ・ん・だ」と遊んでいました。
-
4年生は国語「ごんぎつね」の学習が終わりました。最後に書いた作文を学年だよりから紹介します。 “『青いけむりがまだつつ口から細く出ていました。』で、なぜ終わらせたかをグループで考えたときに、他のグループが言ったことが心に残りました。それは「青いけむりとごんの命がもうすぐ今にも消えそうという表現でやったんじゃないだろうか」と考えていて、私もこの意見じゃないかと思いました。そしてそれを振り返ってみると、兵十も撃った後後悔しているんじゃないかと思いました。『火縄銃をばたりと取り落としました。』という文章ももとに考えたらそうでした。「ごんがかわいそう」という気持ちは変わらないけど、最初の軽い「ごんがかわいそう」よりも、もっともっと「ごんがかわいそう」という気持ちになりました。” どの子の感想もクラスで考え合った分だけ学びが深くなっていました。みんなで学び合うよさです。



音楽会特別時間割が始まりました。小中連携の一つとして中学校の音楽の先生に歌声の指導をしてもらいました。今日は4年生です。いろいろな先生に教えていただくことは、いろいろな感じ方や考え方にふれることができてとてもいいことです。教えていただいた中から、4年生が受け取ったことを歌声として表現してくれるはずです。楽しみです。
-
昨日、5年生が脱穀を行いました。と言っても、脱穀機に干しておいた稲を入れていく作業が主な仕事でした。作業が進むにつれて、お米袋も増えていきます。「今年は多いと思うよ。100kg~130kgかな。」「今までで一番多いかも。」とのことです。5年生が関わってきた田んぼですが、日常の管理は多くの方によるものです。ありがとうございます。脱穀の様子を見ていて印象に残ったのが、落ち穂(脱穀されずに稲束に残っている穂)を丁寧に集めている子どもたちがいたことです。籾からスタートし、お米になるまで時間と手間がかかっています。一粒でも残したら「もったいない」という気持ちもあったのかなと思いました。



左:一列に並んで稲束を脱穀機に入れていきます 中:前からの様子です。左端にいるのが、脱穀し終わった稲束を点検している子どもです 右:カメラを構えていたら、指にトンボが止まりました。最終段階の様子です。稲束の上に座り込んで落ち穂をみつけて、取り出していました。
-
6年生の廊下に「秋の句・歌」が掲示されていました。気がつけば随分と日も短くなり、朝夕の気温も低くなりました。子どもなりに自然の移ろいを感じ表現していると思いました。「木の下は 赤や黄色の じゅうたんだ」「紅葉だ 秋のはじまり 感じるな」「木の下は かれ葉たくさん うもれちゃう」「山の木が まほうにかかり 赤・黄色 たくさんの色に もようがえ」「お彼岸に 目立つ赤色 マンジュシャゲ」「秋深く 山はだ色づけ風にのり 赤黄の雨が ふりそそぐかな」「秋の朝 風が冷たく 手がこおる」「秋の山 カラフルな服に 衣がえ」「見上げると ひときわめだつ 黄金のまり」「秋風が 木々をゆらして 去っていく」「落ち葉降り 山になったら 飛びこみだ」「窓辺から 秋を感じふ おちはかな」 句や歌と一緒にイラストもお楽しみください。