-
 写真:5年生が日本全国の地域調べを始めました。それぞれの農工業の特産品も書かれて掲示されていました 日本にもいろいろな地域があることを学んでいます
写真:5年生が日本全国の地域調べを始めました。それぞれの農工業の特産品も書かれて掲示されていました 日本にもいろいろな地域があることを学んでいます長谷小学校の9月はなかよし月間です。今週から兄弟学級での「仲良し清掃」(お互いの教室のみ)と「なかよし郵便」が始まっています。1年生のところには、早速6年生からのお手紙が届いて子どもたちが喜んだそうです。子どもたちが自分宛のお手紙をもらうなんて、おそらく年賀状くらいでしょうか。考えてみると、大人も同じような状況かもしれません。SNSやメールである特定の人とのやり取りはあっても、個人から自分宛の手紙をもらうことは本当に少なくなりました。お手紙を書くときには相手のことを考えます。そうやってお互いに「思い合う」ことが日常的にあればいいなと思っています。
-

 写真左:一年生教室前のお月様 右:図書館前廊下のお月様
写真左:一年生教室前のお月様 右:図書館前廊下のお月様10日は“中秋の名月”お月見の日でした。新聞でもTVニュースでも「今日のお月様は・・・」と報道がありましたが、家庭では昔からの風習として“お月見”が伝わっているでしょうか?ほとんどの家庭では、お供え物を用意し、飾り付けをしてこの日を迎えたということは無かったのではないかと思います。だから、最近の学校の役割の一つとして「昔からの日本の伝統文化の継承」があると思っています。低学年の生活科で学ぶことが多いです。1年生は教室で先生のお話しを聞きながら、お月見をしました。給食の献立にも伝統文化の継承を感じられることがあります。学校に飾られたお月様を見て、それぞれのおじいちゃん、おばあちゃんから「お月見はね・・・」とお話しをしてもらいながらできたらいいなぁと思いました。
-




写真 左から 事前の打ち合わせ「みなさん、お話しします」の一言で集中し、よく話を聴いていました。 病気の母親と悲しい別れの場面 子どものために今までは猟で打ったことがない猿を狙っている勘助 冷たくなった母猿を手で必死に暖める子猿たちとそれを見てしまった勘助
15日の参観日に3年生が「孝行猿」の劇を発表します。長谷小学校では3年生が毎年行ってきている伝統行事となっています。その年によって、自分たちが表現したいように少しずつ挿入歌や台詞、演出等が変わっています。今日は、本番に備えてお客さん慣れをするために、舞台稽古の見学の案内があったので観劇してきました。感想を一言で言えば「とても立派でした」。声の大きさ、語りかけ方、動作、劇中の準備、片付け、歌、笛・・・子ども9人+先生で時間をかけて創り上げてきていることがよくわかります。「劇」には子どもたちが育つ要素がたくさんあります。教室での座学も大切ですが、地域に学び、地域から学び、自分たちのものとして発表できるようにするところまで、みんなで学び、育つ。それを支える先生もこの劇を完成させるまでどれほどの時間を費やしたことでしょう。入学式の時のあの子が・・・とどの子にも本当に成長を感じ、とても嬉しい気持ちになりました。
-


 写真左:出来上がった作品です 確かに宇宙船やロケットのように見えます 中:突然激しい雨が降り出しましたが、サッカーをして遊んでいた子どもたちはしばらく続けて遊んでいました。雨に濡れるよりも楽しさが勝っていたのです 右:調理クラブです。おいしそうな匂いがプンプンしていました
写真左:出来上がった作品です 確かに宇宙船やロケットのように見えます 中:突然激しい雨が降り出しましたが、サッカーをして遊んでいた子どもたちはしばらく続けて遊んでいました。雨に濡れるよりも楽しさが勝っていたのです 右:調理クラブです。おいしそうな匂いがプンプンしていました休み時間に、廊下に置いてある算数の「かたちあそび」が気に入ったようで、ここ何日か熱心に何かを作って遊んでいる子がいます。私も隣で一緒に作っていましたが、同じ形のパーツを集めては、はめ込んで動かし立体にしていく。時には違う形も選ぶけれど、自分の中のある決まり事にしたがって作っているようでした。話しかけても、返事もないくらい熱中していました。出来上がると「これは宇宙へ行く・・・」と説明してくれました。できた作品を上手に並べて満足そうにピョンピョン跳びはねて喜んでいました。こんなに夢中になって遊べるものが学校にあってよかったと思いました。
-
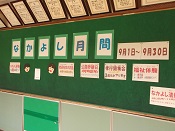



写真:9月は仲良し月間です 「長谷っ子講座」がありました
「あー、体育がやりたい」と言いながら廊下を歩いてきたのは6年生。ここ数日、天候不順でグランドが使えないので、体育でやっている野球型の授業ができていません。加えて、警戒レベル6になっているため、体育館も学年毎遊ぶ時間が決められていて思うように使えません。きっとそういう気持ちが体育の授業が楽しくて「やりたい」と言葉になったのでしょう。学校でそしてクラスでやるから楽しいのです。自分からやりたいと思えることがある、前向きな気持ち、楽しもうとする気持ちがいいなと思いました。