-


 写真:とてもわかりやすい手話でした。どうしてこの手話になったのかという成り立ちも説明していただいたので覚えやすいと思いました
写真:とてもわかりやすい手話でした。どうしてこの手話になったのかという成り立ちも説明していただいたので覚えやすいと思いました2、3年生が「手話」について体験学習をしました。「聞こえない」ことで困ることの一つは、災害等の非常時に音声放送のみで広報される情報がまるで分からないことです。大震災後にもこのことは問題になりました。「だから、小さい時から少しでいいから手話を覚えてもらえると、聞こえなくて困っている人の助けになります」と講師の先生から手話通訳の方を通して教えていただきました。今日は簡単な手話を覚えることから始まりました。「おはよう、こんにちはこんばんは、ありがとう、ごめんなさい、いただきます、ごちそうさまでした、おやすみなさい、さようなら」子どもたちはすぐに覚えてしまいました。どんな人にも生活しやすい社会にするために、日頃から知っている手話もつけて話をするようにしていると、今日教えていただいた手話は使えるようになると思いました。
-
朝、虫取り網を持って登校している子どもたちがいました。理科の学習「秋探し」で使うのでしょう。登校を見守っている方と歩きながら、虫取りの話をしていたら「この辺の子は、いろいろな虫もいつもたくさん見ているから、カブトムシなんかいても余り騒ぐことがないですね。珍しくないからだと思いますよ」という話題になりました。そんな話をしていたら、歩道の隅にカブトムシの雄の立派な成虫を見つけました。子どもたちの反応はといえば、「あっ、カブトムシだ」と言って触るわけでも立ち止まるわけでもなく、そのまま普通に歩いて通り過ぎていきました。確かに珍しくないみたいです。豊かな自然の中で育つ長谷の子どもたちには、カブトムシが身の回りにいるのが当たり前なのだなと改めて思いました。
-

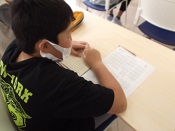
 4年生5年生が点字の学習を行いました
4年生5年生が点字の学習を行いました今朝、6年生が修学旅行へ出発しました。見学場所は児童の希望も入れながら決定し、先日の参観日には事前学習として調べたことを発表していました。6年生が不在だったので、活躍したのが5年生、4年生。朝の放送もゆっくり、ハッキリ、明るい声で行っていました。6時間目のスマイルタイムは、5年生の計画で行いました。「今日は自分たちが楽しむ番ではありません。下の学年の子が楽しいと思うように計画し、進めていく番です」と張り切って進めていました。6年生が不在でも頑張れる長谷の子どもたち。頼もしいです。
-



15日に5年生が稲刈りをしました。様子を見に行った時には、もう半分が刈り取られていて、トラックの荷台一杯に稲束が積まれていました。5年生は休憩する時間も惜しんで、働いている子もいました。長谷の子は、家でも田畑できっとよく働いているし、それが普通になっているのだろうと毎年思います。今年も乾かすプールのフェンスが足りないくらいの収量がありました。今日は、畑から「それ、大きいじゃん」と大きな声が聞こえてきました。行ってみると、2年生がジャガイモの収穫をしていました。そんなに多くの苗を植えたわけではありませんが、バケツ2杯分のジャガイモが収穫できました。このあとの学習では、自分たちが育てた作物を自分たちで調理して食べることになります。「食べること」は「命をつなぐこと」「生きること」でもあります。大事な学習だと考えています。
-



写真左:母との別れ 中:母猿を助けようと必死な子猿 右:熱演した3年生
今日は、参観日と孝行猿集会がありました。朝から何となくソワソワしている子が多かったような気がしました。参観授業では教科は様々ですが「人権教育」に関わる内容を扱いました。友だちのこと、平和のこと、誰もが幸せになれる世の中にするために、日々積み重ねて学ぶ必要があります。孝行猿集会では、3年生の熱演で子どもが親を、そして、親が子を思う気持ちについて、自分のこととして考えることができたと思います。こうした物語を大事に受け継いできた長谷地区に生まれ育つ子どもたちは、これからも優しい気持ちを一緒に育てていくことができるだろうと思いました。